耳の痛み
▼対処
◎鎮痛剤をお持ちでしたら、まず服用してください。
- 解熱用の座薬も鎮痛効果が十分にありますので使用してください。
- 抗生剤をお持ちなら一緒に服用してください。
- 中耳炎、外耳道炎や耳下腺炎などは冷やした方が楽になります。
- 外耳道に入った虫が動いて痛い場合は、油を注入して殺すと痛みは治まります。
◎痛みの強い側を上にして、できるだけ風呂や運動のように体が暖まることは控えてください。
◆コメント
数多くの病気で”耳の痛み”が出現します。また、”耳痛”と言っても原因がはっきりしない場合、あるいは原因に心当たりのある場合、また耳の奥が痛む時、耳の周囲や入り口が痛む時など、”痛み”の原因や場所もさまざまです。
子供で突然の耳痛は、「急性中耳炎」のことが最も多いです。風邪をひいていた時は、特にかかりやすくなっています。「外耳道炎」も多くみられ、プールや耳そうじのあとになりやすく、夏に増加します。
その他「滲出性中耳炎」、虫などによる「外耳道異物」、鼓膜や外耳道の「外傷」、「耳介炎」、「耳下腺炎」、また喉の奥の強い痛みが耳痛と感じることがあります。「神経痛(ヘルペスなど)」や「耳下部リンパ節炎」などもあります。
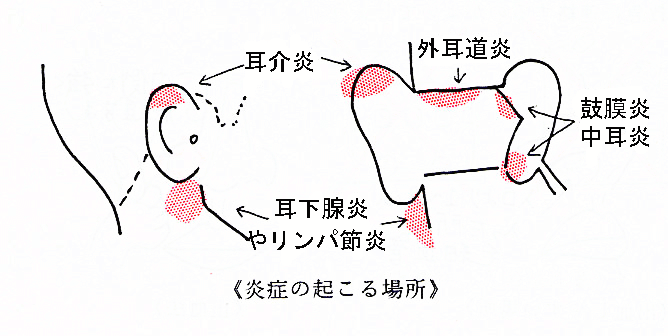
鼻血
▼対処
◎鼻の入口を外側から圧迫してください。(小鼻をつまむように)
- できれば入口に綿花かガーゼのような柔らかなものを詰めて強く押さえてください。
◎座ったままの状態の方が心臓より高くなり、のどの方にも流れにくくなります
- 頭を低くしたり、首をたたいたりしても止血効果はありません。
- 風呂上がりや運動した後のように血圧が上がっていたり、詰めたものをあまり何度も入れ替えたりしていると止まりにくくなります。
- 上述のようにしていても、のどの方からたくさん出血する場合は、鼻の奥の方からの出血の可能性がありますので、早めに消防署などの救急に連絡するのがよいでしょう。
◆コメント
子供の場合の”鼻血”は、ほとんど入口の内側部分(だいたい鼻の穴から1~2cm入った皮膚と粘膜の移行部付近)よりのものです。
この部分は毛細血管が集まっていて、引っかいたり触ったり、鼻をかんだりあるいは何もしないのに出ることもよくあります。 風邪を引いていたり、鼻炎を持っていると粘膜が弱くなっているため出血しやすくなります。
大人の場合もこの入口部分からの出血が多いのですが、鼻の奥の方の血管や鼻たけ(ポリープ)から出ることもあります。高血圧、血液病、肝臓病、腎臓病などの基礎疾患があると、大量に出たり非常に止まりにくくなります。
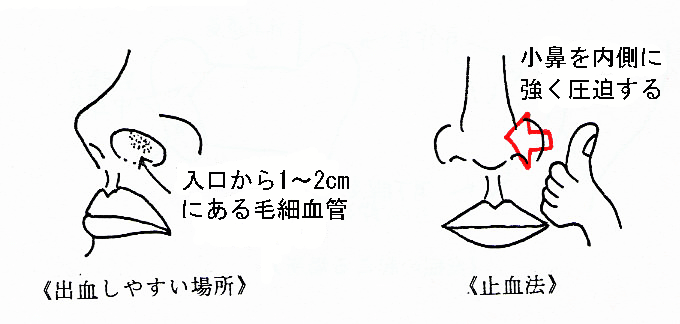
めまい
▼対処
◎めまい発作が起こったときは第一に安静が必要です。
- 意識と呼吸がしっかりしているか注意してください。
- トラベルミンのような酔い止め薬や吐き気止め薬、あるいは精神安定剤、抗ヒスタミン剤があれば服用してください。
- ”めまい”は、吐き気や冷や汗などの”自律神経症状”を一般に伴いますので、とても内服できないと思うときは無理しないでください。
◎発作時に乗り物に乗ったり、頭を振ったり、体を急に動かしたりすると逆にめまい症状を悪化させることが多いので、発作がおさまっていても十分に注意してゆっくりと動作してください。
・ 風呂なども避けた方がよいと思います。
◆コメント
「グルグル回る(回転性)めまい」、「物が流れたり、揺れて見えるめまい」、「ふわっと浮いたようなめまい」、「眼の前が暗黒になるめまい」等をすべて広い意味で”めまい”と呼びます。
大きく分けて耳性(「メニエル病」、「突発性難聴」など)あるいは中枢性(「脳出血」や「脳梗塞(血管がつまる)」、「脳腫瘍」など)があるといわれていますが、かなりのものは原因不明です。
典型的な耳性めまいでは、「回転性めまい」に、「耳鳴り」や「難聴」、あるいは「耳閉塞感(耳がつまったような感じ)」を伴ったりします。(実際の症例では、症状がそろわず、断定的に言えないことが多いですが。)
ただし、”めまい”の中には脳の出血や梗塞が潜んでいることもありますので注意が必要です。
そのような場合はめまい以外の症状、たとえば「意識障害」、「ひどい頭痛」や「手足のしびれ」、「しゃべりにくい」などの神経症状が出現することも多いのです。生命に関わる重大なめまいの場合は、早急にMRIやCT、血管造影などの早期の診断と治療が重要となります。
このような危険なめまい以外は発作中は横になって静かにしています。
”耳性のめまい”では、悪い方の耳を上にした姿勢の方が楽なようです。めまいの方は、肩こりのひどい人や血圧が不安定な人が非常に多く、実際には血液の循環障害、循環不全を疑う例が多いと推察されます。
耳・鼻・口の外傷
▼対処
- 耳掃除中に耳を突いたとき(外耳道鼓膜外傷)に出血したら、綿やティッシュなどを入り口に詰めておけば、出血はたいてい止まります。
- ”鼻の外傷”も止血さえすれば、それ程あわてる必要はありません。
- ”口の外傷”はよく出血しますので、場所がわかればガーゼなどで圧迫してください
◎血液を飲むと出血量が分かりませんし、呼吸困難や吐き気の原因にもなりますので、絶対に飲み込まないようにしてください。
・ 出血が続いたり、傷が大きければ縫う必要がありますので、消防署などの救急へ連絡してください。
◆コメント
”耳の外傷”では耳掃除中に耳を突かれた、あるいは手に当たられて突いた、そしてその後、耳が痛い、聞こえにくい、出血してきたということが多いようです。耳の場合はそれほど重症でないことが多く、たとえ鼓膜が破れたとしても感染さえ起こさなければ、時間はかかりますが非常によく治ります。
”鼻の外傷”はあまりなく、交通事故や転倒などが原因です。
また、”口の外傷”も少数ですが、舌を噛んだり、乳幼児が箸でのどを突いたり、物をくわえていて転んだときに口内や唇を傷つけることがあります。口腔内は粘膜ですので、治りも早いですし、傷もほとんど残りません。いずれの外傷もあまり触らず不潔にはしないでください。

異物
▼対処
- ”耳の異物”のほとんどの場合、あわてる必要はありません。自分で取ろうとして外耳道や鼓膜を傷つけることの方が多いのです。
- 前述(「耳痛」の項)のように生きた虫の場合は殺しておいたほうが痛くないです。
- パーマ液のような刺激性の物が入った場合も水で軽く洗った方が良いでしょう。
- ”鼻の異物”も無理に取ろうとすると出血することが多く、耳鼻科医 に取ってもらうのがよいでしょう。
- 魚骨などの”口やのどの異物”が見えるなら、電灯で明るくしてピンセットか何かで取ってください。
◎はっきり見ずに、指で引っかいたり、ご飯などを丸のみして取ろうとしないでください。
・ ”食道異物”は、水や食事がスーと入るようなら既に胃に落ちてしまった可能性が大です。
◎”気道異物”の場合は判断が難しいので、無理に処置せず、消防署などの救急に連絡してください。
◆コメント
”耳や鼻の異物”は耳に虫が入ったり、海水浴で砂が入ったり、乳幼児のように自分でおもちゃ等を耳や鼻に詰めることが原因です。”鼻の異物”は奥に入るのを心配される方もありますが、鼻入口から取れないような物は、奥に吸い込まれることもほとんどありません。ただし、乳幼児の”鼻の異物”の場合、まわりが気づかず、片方の鼻から膿のような鼻汁が続いているだけのことがありますので、ご注意を。
また、魚骨がのどに刺さる”咽喉頭異物”はもっとも多く、魚骨、義歯、薬のケース等の”食道異物”もときどき見られます。指で触ったり、ご飯の丸のみのように、自分であまりいじくりまわすと、後日診察した時、かえってどこに異物があったのか、痛みの原因が炎症だけなのかどうか、よくわからなくなることがあります。そのような対処はできるだけ控えてください。
食道異物もたいていあわてる必要はありませんが、痛みや異物感が残っているようなら、胃カメラや造影検査を受ける方がよいでしょう。 もっとも恐ろしいのは、”子供の気管支異物”です。何かを食べているときに、泣いたりびっくりしたとたんに飲み込んでしまったりします。特に豆類などが気管・気管支に入ったときは、症状もはっきりしない事が多く、後に急速に呼吸困難、肺炎になったりします。

喉の痛み
▼対処
- まず鎮痛剤を服用してください。うがいやトローチも有用です。
- 抗生剤があれば、細菌による扁桃炎などにはよく効きます。
◎辛い物、酸っぱい物、熱い物、かたい物などの刺激物を絶対に避けてください。
- できるだけ水分を摂取してのどが乾燥しないようにしてください。
◆コメント
ほとんどが炎症によるものです。炎症の原因は、単純な「咽喉頭炎」、「扁桃炎」、「顎下腺炎」から、非常に痛みが強く嚥下困難も伴う「扁桃周囲膿瘍」、時に呼吸困難も伴う「喉頭蓋炎」までさまざまです。扁桃炎周囲膿瘍や喉頭蓋炎では、切開や抗生剤の点滴が必要なことがほとんどです。
また、「手足口病」や「ヘルパンギーナ」、「アフタ性口内炎」も時として”のどの痛み”として感じます。
呼吸困難
▼対処
- ”喘息”では横になるより、座った方(起座呼吸)が楽です。
◎いずれの原因でも自分で対処するのはかなり難しいので、早期に診てもらった方がよいでしょう。
- ・息が止まっている場合は、自分たちで最低限の救急救命処置が必要 となります。
◆コメント
代表的なものは、咳、喘鳴(ヒューヒューやピューという)を伴う「気管支喘息」でしょう。
一般に喘息の場合、息を吸うよりも吐く方がしんどくなります。逆にのどの炎症が原因の呼吸困難は、息を吸うのが苦しくなります。
これら以外にも多くの原因があり、異物、腫瘍、上気道炎、気管支炎、肺炎さらに心臓病でも現れることがあります。しかし原因によっては”気管内挿管(口から気管に管を入れる)”や”気管切開(前頸部を切開してここから息をさせる)”が必要なこともあり、自分での判断は難しいと思います。
もちろん餅がのどにつかえて窒息している場合などは、引っ張り出したり、吸い取ったりして救命してください。
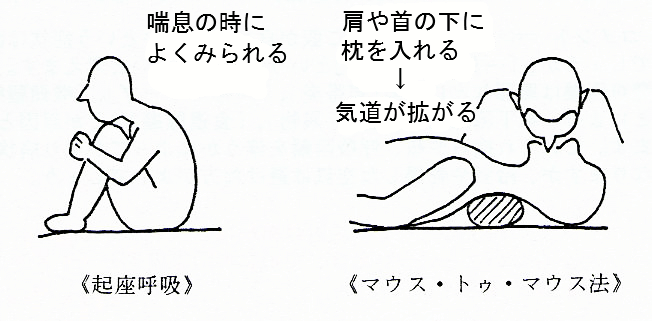
発声・嚥下困難
▼対処
- 呼吸が正常ならそれほどあわてる必要はないでしょう。
◎発声困難なときは決して無理に声を出さないでください。声帯ポリープや声帯結節になったりします。
- ささやくような声も声帯に負担をかけますので、普通の大きさで必要最小限の会話を心掛けてください。
- 嚥下困難の場合も無理に食べないで、できれば水分のみの補給にとどめて、早めに原因を調べて対処する必要があります。
◆コメント
声が出ない、ご飯が食べられないという症状は困るでしょうが、「一刻をあらそう」というものは少ないと考えます。
発声困難は風邪などによる「声帯炎」、「声帯ポリープ」、「喉頭腫瘍」などにより、嚥下困難は「炎症」、「異物」、「食道腫瘍」などが原因となります。それぞれ痛みや咳、呼吸困難を伴うかによってかなり病状は異なりますが、冷気や乾燥した空気は避けた方がよいでしょう。
