補聴器
補聴器についての説明。やや専門的です
- 有用性について
- 補聴器の構造
- 種類
- フィッティングと調整
新しい補聴器(工事中)- 問題性
1、有用性について
「補聴器は、雑音ばかりで肝心の言葉が全然わからん!」
よく補聴器を持っておられる御老人がおっしゃるセリフです。ほんとうにそうでしょうか?
難聴にはいくつものタイプがあります。
聴力図は横軸が周波数(音の高さ)、縦軸が聴力レベル(音の強さ)を表しています。
右に行くほど高い音、下に行くほど難聴の程度がひどいことを示しています。
補聴器は一種の増幅器で難聴の形や程度によって、増幅する度合いや音質の調整、出力制限(あまり強大音を出さない装置)などを個々に合わさなければなりません。全音域を増幅したり、あるいは高音域のみ、時に低音のみの増幅が必要なこともあります。
ですから補聴器が合っていなければ冒頭のような意見が出てくるわけです。後述しますが、もちろん補聴器にもまだ多くの問題点があります。
「補聴器はどのくらいの難聴から必要ですか?」という御質問をよく受けますが、このレベルの難聴なら補聴器が必要といった明確な基準はありません。ご老人の場合でもまだ第一線で活躍されている方や趣味の会、友人が付き合いで忙しい方は是非補聴器を使われたほうが良いでしょう。
しかし一人暮らしで何日間も誰とも喋ることがない方が、ドアのチャイムや電話のベルだけを聞くために一日中補聴器を使用するのは無意味です。
ただしこのような外部からの何の刺激もない生活が脳や体にとって良い環境とは思えませんので、生活環境そのものを変化させ、むしろ補聴器の必要とされる活気のある生活を過ごされる方が良いのではないでしょうか。
補聴器への要求は様々です。
テレビ・ラジオが聞こえない、対面での話がわからない、騒音の中での話や早口がわかりにくい、小さな声が聞こえない、遠くで呼ばれても聞こえない、自動車の音や警笛がわかりにくい、等々。その人の聴力、仕事、生活環境、趣味、使用場所もいろいろです。
一般に補聴器を合わせる場合、その人の難聴の半分くらいを補うように音を増幅しますので、補聴器を使用しても健聴者と同じ聞こえにはなっていません。
ひそひそ話や遠方からの呼び声などはわかりにくいですし、早口をわかりやすくすることも難しいのです。
周りの人も大声ではなくゆっくりとはっきりと喋りかけることが大切です。
補聴器の重要な目的は人の言葉を聞くことですが、 当然周囲の雑音も入ってきます。実際には健聴者も聞いている環境騒音なのですが、これがうるさいと言う人も多くいて、この点ある程度馴れも必要です。
さらに電車の中のように健聴者でも聞き取りにくい環境では補聴器の使用は一層難しくなります。
テレビやラジオの音を聞くだけならヘッドホンのほうがきれいに聞こえるでしょうし、電話だけなら音量をかなり大きくできる電話機があります。
個人個人にとっての補聴器の有用性は、補聴器の長所・短所を知り、どのように使いこなすかに係っています。
その際何よりも必要なのが、いろんな音や人の声を聞き、いつまでも社会に参加したいという意欲です。
最近の補聴器は従来の箱形、耳かけ形、眼鏡形、耳穴形に加え、FM式やデジタルを応用したもの、CICと呼ばれる外耳道に全体が入ってしまう超小型のものまで出現してきました。補聴器の選択幅も広がり、音質もかなり向上しています。
将来は欠点をすべて克服した補聴器が出てくるでしょうが、現在は耳や難聴の診断と聴力の程度を調べ、補聴器をきっちり合わせてから購入すること、聴力の観察と補聴器のメインテナンス、そして補聴器の有用性を最大限に引き出せるように十分に使い込むことが重要です。
近年の急速な老齢化社会を迎えるに当たり、補聴器の必要性が訴えられて久しく、ハウリング防止やノンリニア増幅などの新しい機能を持つ補聴器も確実に増えています。しかし補聴器の基本的なハードの部分はそれ程大きくは変化しておらず、逆にフィッティングや評価などのソフトの部分は遅れています。
今回、補聴器の現状として補聴器の構造や種類、そのフィッティング、新しい補聴器の流れについて述べ、そして最後に今日抱えている補聴器の諸問題について考えます。
2、補聴器の構造
補聴器の次のような構成を持っており、基本的に音は(マイクロホン)→(アンプリファイアー)→(イヤホン)と流れていく。 補聴器は増幅器であり、構成的にはラジカセ、ステレオなどの家庭用音響機器によく似ている。
入力部が補聴器ではマイクロホンであるのに対して、それぞれCD、レコード、カセットテープとなっている。
出力部は補聴器の場合イヤホンであるが、家庭用音響機器ではほとんどがスピーカーかヘッドホンである。
プリアンプ・メインアンプ部で音質の調整や音の増幅が行われるのは両者同じで、補聴器では機種により出力制限装置が付属する。また補聴器では外耳への固定やハウリング防止、音質調整の目的のため、イヤホンの先にイヤーモールドを付けることがある。
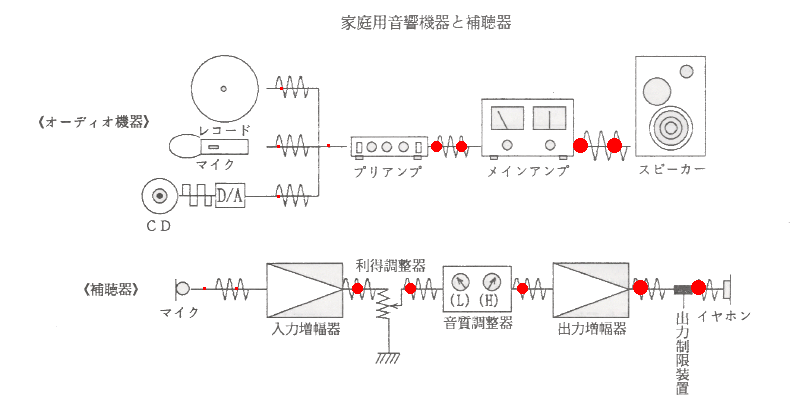
3、種類
補聴器の種類は、分類法により次のように分けることができる。
- 形状
ポケット型、耳掛け型、耳あな型(カスタム、カナル)、眼鏡型 - 音の伝え方
気導、骨導、CROS、FM - 増幅の程度
軽度、中等度、高度、重度難聴用 - 構成回路
アナログ、プログラマブル、デジタル
一般には形による分類がなされることが多く、それに従いそれぞれの補聴器の特徴を述べる。耳かけ型と耳あな型をひとまとめにしてイヤーレベルタイプと呼ばれることもある。
《ポケット型》
- 【長所】
- 補聴器の操作が簡単
- ハウリングが少ない
- 電池が長持ち
- 比較的安価
- 【短所】
- 大きくて目立つ
- コードなどが邪魔
- 衣服によるバッフル効果や擦れる音が入る

《耳掛け型》
- 【長所】
- 小形で目立ちにくい
- 音源がわかりやすい
- バッフル効果がない
- 【短所】
- ハウリングしやすい
- 取り扱いがやや難しい
- 電池寿命が少し短い
- やや高価

《耳あな型》
- 【長所】
- 小形で目立ちにくい
- 音源がわかりやすい
- バッフル効果がない
- 【短所】
- ハウリングしやすい
- 取り扱いが難しい(特にカナル)
- 電池寿命が短い
- 比較的高価(カスタム、カナル)

《眼鏡形》
- 【長所】
- 目立ちにくい(眼鏡既使用者)
- CROS、骨導式として使用できる
- 【短所】
- 眼鏡が大きくなる
- デザイン、機種が少ない
- 比較的高価

長所、短所というのは相対的なものなので、小さくなって目立ちにくくなれば、当然取り扱いは難しくなり、電池も小さくなる。
我が国の補聴器出荷台数は、約39万台(1995年)のうち、およそ箱形1%、耳かけ形45%、挿耳形36%、眼鏡形0.7%であった。
一方アメリカでは総出荷台数約146万台(1994年)のうち、箱形0.2%、耳かけ形19%、挿耳形78%、眼鏡形0.1%で、日本に比べて約4倍の補聴器販売台数があり、その8割弱が挿耳形となっている。
近年我が国でも耳あな型が4割を超え最も多く、次いで耳掛け型が続いている。
4、フィッティングと調整
補聴器のフィッティングの概略を述べると、医療機関の場合来院患者は一般的な問診、視診などの耳鼻咽喉科的診察を経て、聴覚の評価としての純音聴力検査、不快域値(ダイナミックレンジ)の測定、語音聴力検査等が行われ、さらに詳しい問診により補聴器適応の是非が決定される。
次に装用耳の決定と補聴器の選択がなされ、音質調整、出力制限の程度、イヤモールドの必要性などが検討される。次にこのように仮決定された補聴器について評価がなされる。
評価の結果不満足な点があったり、改善すべき余地があれば、さらに再調整が行われ、場合によっては補聴器の選択からやり直さなければならない。
そして最終的には、貸出による試用や購入後実生活での再評価、再調整が繰り返し行われていく。
▼補聴器の選択法について
補聴器の選択とは形状や機種の選定でもあるが、どのような利得、周波数特性の補聴器を選ぶかということでもある。多くの選択法が提唱されているが、ここでは最も一般な規定選択法であるハーフゲイン法とPOGO法について説明する。両法ともオージオグラムの聴力レベルから利得、周波数特性を求めようとするものである。
- ハーフゲイン法
- 純音聴力レベル(HL)の各周波数の1/2の値を挿入利得とする。
- Berger法
- ハーフゲイン法と似るが、各周波数の次の値を挿入利得とする。
500Hz:500HzのHL/2、1KHz:1KHzのHL/1.6、2KHz:2KHzのHL/1.53KHz:3KHzのHL/1.7、4KHz:4KHzのHL/1.9、6KHz:6KHzのHL/2
- ハーフゲイン法と似るが、各周波数の次の値を挿入利得とする。
- POGO(Prescription of Gain/Output)法
- これもハーフゲイン法が基本であり、1KHz以上では各周波数のHLの1/2の値を用いる。250Hz、500HzについてはHLの1/2値から250Hz:-10dB,500Hz:-5dBの補正を行い、それを挿入利得とする。
▼補聴器の調整について
補聴器の調整には主なものとして3つのものがある。「音量調整」と「音質調整」、「出力制限」である。
それぞれの調整装置は機種によって付いていなかったり、リモコン式あるいはパソコンなどのインターフェースを用いるものもある。
「音量調整」は、音量調整装置すなわちボリュームやサブボリュームを用いて行う。文字通り音の大きさを調整するものだが、普通1~2m離れた話声が聞きやすい音量にしておき、場面に応じて調節する。もちろん補聴器の増幅力により、ある程度調整幅は制限される。
「音質調整」は、音質調整装置によって行われる。箱形や耳かけ形では、小さなトリマーに「TONE」、「HIGH」、「BASS」、「H」、「L」などと書かれており、この装置により周波数特性の低音部のゲインを下げたり、高音部をアップしたりできる。 理想的には裝用者が聞きやすくて疲れにくい、そして語音了解度も良くなるような調整が選択される。音質の調整はこれ以外に前述のイヤーモールドやベント、ダンパーといった装置でもある程度調整可能である。
「出力制限」は、出力制限装置により行われる。一般に「PC」、「OPC」、「MOP」、「COMP」等と書かれたトリマーであるが、 その表示法や方法は各社、各機種さまざまである。簡単に言うと、 ピーククリッピング方式、 オートゲインコントロール方式、 コンプレッション方式に大別できる。 出力制限装置を効かせ過ぎると音の歪みは増大するが、感音難聴者ではたいていの場合ダイナミックレンジが健聴者と比べてかなり狭くなっているので、 衝撃音や大声などが不快域値を超えて響かないようする重要な装置である。
▼評価法について
補聴効果の評価は音場での装用域値測定や音節、単語、文を用いた語音了解度検査、 あるいは検者との対面での会話聞き取り能力などの了解度に関する事柄と、患者の音質や装用感などに関する主観的評価とに分かれる。
了解度の改善度と主観的評価のどちらを優先させるか難しい問題だが、どちらを優先させるかについてまだ定まったものはない。
▼実生活での試聴・装用
騒音の多い実生活での使用では、フィッティング時にはなかった不満点や訴えが多く見られる。
「周囲の雑音がうるさい」、「話の内容がわからない」、「自分の声が大きい」、「ハウリングがする」、「食器や紙の音が響く」等々があり、それぞれ再調整などの対策を講じたり、補聴器の限界や使用法をカウンセリングするだけのこともある。
その後聴覚管理を含め何度かのアフターフォローが必要である。
5、新しい補聴器
工事中
6、問題性
補聴器の問題というのは非常に多岐にわたっています。補聴器の機器自体の問題であったり、医療とのかかわり、システム全体の問題もあります。
補聴器自体も適合システムもまだ発展途中ということもあり、補聴器使用者の不満はたいへん大きいものです。
以下、問題点につき分類して簡単に述べたが当然それぞれの問題は密接に関連しています。 将来、補聴器自体が完全自動適合装置のようなものを持つようになればかなりの問題は解決するかもしれませんが。
▼補聴器供給システムの問題 →「誰がどのようなことをどの程度するべきか」
現在補聴器は自由に販売されています。補聴器のフィッティングが行われるのは、医療機関であったり、教育機関であったり、販売店(それも専門店から眼鏡店まで幅広い)であったりします。
所によってはフィッティングなしに聴力検査もせずに補聴器が販売されることもあり、そのため高価な補聴器を買わされたり、いくつもの補聴器を持っている人達も多いのです。
補聴器はCICのように小型化し、より外耳道に密着し、より鼓膜に接近してきています。
耳穴型補聴器やイヤモールドの耳型採取では危険性が増大し、採取が医療機関でなされるべきか、これも今後議論の多い問題です。
▼聴覚生理と補聴器適合 →「どのような基準で補聴器を合わせれば良いのか」
我々人間はどのように音を聞き、音声を分析し、騒音の中から言葉を拾い上げているのか、聴覚生理の不明な点は多いのです。
そのため補聴器選択、補聴器調整、補聴器評価、さらに装用耳の決定や両耳装用の効果判定が困難なものとなっています。 難聴者、特に感音難聴では 不快域値は健聴者のそれに近い、 ラウドネス異常増大(リクルートメント現象)、周波数選別能の低下、 時間分解能の低下などが認められるのでさらに補聴器の適合が困難なものとなっています。
また単音節、単語、文章、会話能力また発話速度それらがどのように関連し合っているのか、日常コミュニケーション能力の向上と補聴器の快適な装用、 共に満足させるにはどうすればよいのか、どのような手順で何の検査を行えばいいのか。現在それらすべてに答えはなく、多くは経験や試行錯誤によってなされているのが現状です。
▼リハビリテーション、アフターフォロー →「誰がどのようにするのか」
聴覚管理、補聴器による聴力障害、イヤーモールドによる外耳道皮膚炎など医学的に未解決な問題も存在します。
補聴器の供給システムが混沌としているため、アフターフォローが十分に行われておらず、補聴器の使用者の障害や苦情がどのように処理されているのか 、全くわかりません。
老人の意欲や社会的状況とも関係していますが、 補聴器装用後のリハビリテーションが有効かさえ不明でなのです。
▼補聴器自体 →「理想の補聴器とは程遠い状態である」
最近のデジタル技術の発達で、ハウリング、サイズ、電池、歪みなどかなり改善されつつあるが、まだ多くの問題を残しています。 もちろんこの中にはサイズと取り扱いやすさのように相反する問題も含まれています。
しかし最低考えておかなければならないのは、補聴器を使用するのは新しい機器や使用法をすぐに習得できる若者ではなく、 多くの場合テレビのビデオ録画もなかなか覚えられない老人であるということです。
以下、改善の必要と思われる項目を列挙しました。
- 音質 ・会話の内容がわからない
- 明瞭度、発話速度(時間分解能)
- 遠くの会話、大勢の中での会話
- ノイズ、環境騒音の軽減
- 出力制限、歪み、ダイナミックレンジ
- ハウリングの軽減
- サイズ、取り扱いやすさ
- 表示の統一 ・ボリューム、調整の簡便さ
- 電池交換、電池寿命 ・価格
デジタル技術の進歩で多くの新しい機能を有した補聴器が誕生し、多機能ゆえに選択範囲は増えたましたが、同時に複雑さも増しました。補聴器のフィッティングもそれに合わせて進歩する必要があります。
また福祉介護の問題同様、難聴者や補聴器装用者を支える組織、態勢がありません。補聴器使用者が気軽に相談できる機関が欲しいものです。
我々医療機関、教育機関、メーカー、補聴器販売店等がなすべきことはまだまだ多いと思われます。
