体のしくみ
耳と鼻の構造と仕組みについて
耳の構造と仕組み
耳の役割は大雑把に言うと、①聴覚-音を聞く、②平衡-バランスをとる、という2つです。
外側より耳介、外耳道、鼓膜、中耳(腔)、内耳と呼ばれています。
耳介と外耳道は皆さんご存じでしょう。外耳道は長さ約3㎝しかなく、奥の方(内側)の半分は皮膚が薄く非常に敏感で、耳掃除などですぐに傷がついたり痛くなったりします。主に耳垢がたまるのは外側半分です。
鼓膜は直径1㎝弱の膜で外耳道のつきあたりに位置します。音に応じて振動するので半透明で薄くできています。
鼓膜があるため、耳に水が入ってもこれ以上奥の方(中耳)には入ってゆきません。
鼓膜は膜ですので、これがへこんだり、癒着したりすると正常には振動せず、難聴を生じます。
中耳には鼓膜の振動を伝える3つの小さな骨(耳小骨=ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨=人体の中で最も小さい骨)があります。
この耳小骨で伝えられた音の振動が最後に内耳(神経器官)に入っていき、電気信号に変換されて脳へと伝わっていきます。
中耳腔は粘膜で覆われており、耳管という管で鼻の奥(上咽頭あるいは鼻部咽頭腔といいます)と通じています。
この管は中耳腔の気圧の調整の役割をします。
炎症が外耳道で起これば「外耳道炎」、中耳では「中耳炎」と呼ばれます。なお「内耳炎」というのは稀にしか起こりません。
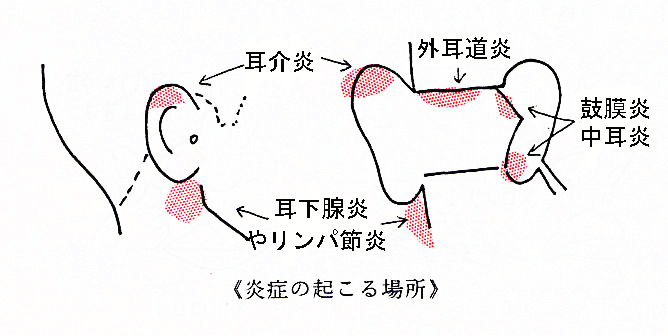
内耳は、側頭骨という骨の内部に埋まっています。側頭骨の中に骨迷路という複雑な形の空間があり、そのなかに膜迷路という液体(リンパ液)を含んだ袋が存在します。蝸牛と前庭を構成しており、聴覚と平衡機能の役割を担っています。
鼻の構造と仕組み
鼻の穴の中の空間は、鼻腔と呼ばれ、鼻中隔という中央の仕切りで左右に分かれています。
奥にいくと鼻中隔はなくなり、1つの空間になります。
そして咽頭につながっていきます。
鼻の中には外側から鼻甲介と呼ばれる粘膜の突出した大きなヒダがあります。
鼻に吸い込まれた空気は、この鼻甲介の間や鼻中隔の横を通って、咽頭に入ってきます。
空気は即座に、加温や加湿され、空気中の塵や病原体が除去され、体内に送りこまれます。
また、その空気から匂いを感知しますが、これは嗅球という鼻腔の上部にある嗅覚感知組織が行います。
鼻甲介の表面に覆われた粘膜は、鼻水を分泌します。
また表面には血管が多く密集しているおり、粘膜を膨張させたり、収縮させたりします。
そのため、時に鼻づまりが起こったりします。
鼻の病気により本来の働きがなくなり、いろんな障害が発生します。
副鼻腔は鼻腔の周囲にある空洞を指します。左右それぞれ4つからなり、
鼻腔と同様に粘膜で覆われていて、細い開口部で鼻腔とつながっています。
副鼻腔に外界から粒子が入ると鼻腔と同様の粘液にとらえられ、線毛の働きで開口部から鼻腔へ運ばれます。そして鼻腔から外界へ排出されます。
ただ開口部は非常に狭いため、かぜやアレルギーなどで粘膜が腫れて塞がってしまいます。
それにより副鼻腔の炎症や感染が起こります。これが副鼻腔炎、あるいは蓄膿といわれている状態です。
